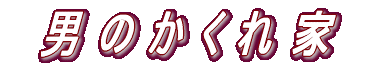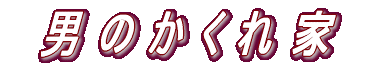|
ジャーナリスト出身の芥川賞作家、辺見庸氏は、米中枢同時テロ後の危うい時代状況に果敢な発言を続ける論客の一人。空爆作戦下のアフガニスタンを取材し、さらに米国で言語学者ノーム・チョムスキー氏と対談するなど、「テロ後」をめぐる考察を重ねてきた同氏は、「テロ」や「正義」の意味合いが米国の論理にじゅうりんされていると力説。その点では個々人の価値観が問われる「内面」の問題と指摘するとともに、「意味の収奪」に対置した言葉の再定義が迫られていると訴えた。(聞き手 共同=山崎博康)
■9・11以後の変わりようをどう見ているか。
「9・11というのは、いわば毒性の強い試薬だった。それが二十世紀のすべてを象徴する米国の中枢に浴びせかけられた。だからこそ、今までの世界の虚像、幻想がはぎ取られたと言える」
「露出したのは、欧米民主主義の意外な暴力性、国民国家の偽善性、人間の無慈悲、知の無力だ。もっとがくぜんとするのは、とうの昔に終えんしたと思っていた植民地主義、あるいは近世や中世という過去の闇が全く払しょくされていないことだ。歴史の古層が実は相当、力を持っていた」
「もう一つは、ブッシュ米政権による意味の強要、意味の収奪ということ。善悪とか、文明や野蛮とか、神や正義とか、世界の存在の根源にかかわる意味を自己流に統制し始めた。圧倒的な武力を背景にして、米国が定義した意味を共有するよう世界に迫っている」
「意想外なことに、ブッシュの驚くべき反知性的な定義が力を持ち、世界は事実上、それによって制圧されている。9・11がもたらした状況は、だから、深く人の内面にかかわっている。意味の強制、独占ということでは、われわれの内面世界がかなり侵略されていると言ってもよい。わたしがいきり立って米国の空爆作戦などに反対しているのは、そのためだ」
■「意味の収奪」で象徴的なのは「正義」という言葉だと思うが。
「ブッシュは言葉を深く吟味していない。米国の存在、米国の様式、米国の力、米国の発想…それがブッシュの正義なのだ。これらを世界に受容させていく。ここに戦争行動の主たる動機がある」
「経済発達国はブッシュ流の正義に内心まゆをひそめ、舌打ちしているのに、事実上は抵抗しようとしていない。むしろ、暴力的に協調しつつある。グローバル化の利害が一致するからだろう。だから、列強が弱小国を撃つ異様な戦争の構造が世界的に拡大している。メディアがこれに同調してはならない。メディアは米国による世界の定義を覆さなければならない」
■非対称性で浮かび上がるものは。
「世界は一度だって対称的であったためしはない。それは南北問題、階級格差、貧富の差という形で言われた。光も水も資本も偏在する。加えて注目しなければならないのは、情報の非対称だ。過剰に発信される情報がある一方で、全く語られない貧困国もあり、それが非在空間にされてしまう」
「9・11でアフガニスタンが脚光を浴びて絶対的な貧困が明らかになったが、国際社会はまたぞろ忘れ始めている。世界中にあまたあるこうした非在空間の闇が、日夜、列強への復しゅう心を育てている」
■対テロ戦では英米に植民地主義復活を唱える論調も表れている。
「9・11以降の時流に乗り、保守主義者が力をつけている。新植民地主義的な論理で世界を再統一しないとテロはなくならないなどと学者がまことしやかに書き、それを米国の有力紙が掲載したりする。かつてなかったことだ。反テロ同盟を形成し始めてから、保守派論調が下支えする戦争構造ができつつある。今は、広い意味では戦時下だと思う」
■米国には核軍拡に突き進む危うさがある。
「戦術核が今使われていないのは、単なる偶然にすぎない。米国はアフガンで事実上は戦術核を使ったも同然だ。デージーカッター(特殊大型爆弾BLUー82)とかサーモバリック爆弾とか。一番恐ろしいのは、冷戦型の抑止力としてではなく、むしろ有効であれば積極的に核を使おうという今の米国の政権の考え方だ。国際社会に与える影響は極めて大きい。9・11以後の米国の対応が、もともと危うかった戦争抑止の梁(はリ)を取り払ってしまった」
■テロの根源についてはどう考えるか。
「あなたのいうテロの概念は米国的な定義に引きずられていると思う。わたしはテロという普遍概念は存在しないと思っている。東ティモールの独立運動も反ナチ闘争もテロといわれた。米国に反抗するのはすべてテロだとされる。そういう(点を踏まえた)定義のし直しがメディアには必要だという気がする」
「反国家テロには歴史的な正当性があるものも少なくない。マスコミではそういう検証が全然なされていない。例えば、日本が強引にでっちあげた満州国なる国への武装闘争は、テロと呼ばれても正当性があるのではないか」
■「民族」や「国家」を超える生き方を模索する識者もいる。二十一世紀の生き方として示唆するものはあるだろうか。
「怒濤(どとう)のようなグローバル化の流れの中で、逆に世界中で国家主義的な考えが台頭してきている。米国型にすべて地ならししていく力への反作用としての国家意識、自民族優越主義など、古典的共同幻想を求める傾向はむしろ強まっている。グローバル化は決して国境や国家概念を取り払っているわけではない」
「今大事なのは言葉の力、表現者の力だ。(ポーランド詩人)シンボルスカの詩的世界観は素晴らしいものがある。『どの世代にも二種類の人々がいる。個人としての魂を持つ人と、集団的な魂を持って生まれてくる人がいる』という表現は、政治の言葉で語るよりよほど説得力があると思った。思想の画一化というのは、日本だけではない。地球規模の同時反動化のようなものがあると思う。その中で大事にしなければならないのは個人の魂であり、個人の表現力だ」
■既成の政治的枠組みを超える非政府組織(NGO)の役割に期待する発言もある。
「昨年の主要国首脳会議(ジェノバ・サミット)の際の反グローバル化団体の動きなどは、かつてなくラジカルだった。NGOの一部が世界観を持ち始めた。まだ体系的ではないが、冷戦構造崩壊後の世界に対し、はっきり異議申し立てを始めている」
「ただ、ある意味で犯罪的だと思うのは、一月のアフガン復興会議でNGOが米国の戦争犯罪を取り上げず、間接的に追認してしまったことだ。NGOは日本の戦争参加や有事法案にもっともっと抵抗すべきだと思う」
■日本のかかわり方をどう見ているか。
「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)寧辺の核施設をめぐる1993年から94年にかけての米朝危機は再検証したほうがいい。その際の米軍の臨戦態勢が結局は周辺事態法や有事関連法案の骨格をつくらせている。米朝危機は必ずまたやってくると思う。日本の有事とは具体的には朝鮮有事なのだ」
「ずっと中国問題を追ってきたが、極東アジアで一番具体的に発火点となるのは朝鮮半島だろうし、その決定的な局面はそう遠くないうちに起きるのではないか。日米の軍事当局者は恐らく今の北朝鮮政権の崩壊後のことを考えている。そのシミュレーションは彼らにとって焦眉(しょうび)の課題となっている」
■メディアの役割についてはどう考えるか。
「メディアの翼賛化はポイント・オブ・ノーリターン(後戻りがきかない地点)を超えている。有事法制に肯定的なとらえ方をし始めたのは戦後初めてだ。メディアが権力化し、権力がメディア化して、双方が混然一体となリ全体主義構造をつくってしまっている。そこに犯意というものがない。その怖さをつくづく感じる」
|