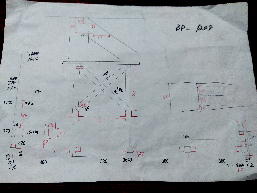

自作の部屋
何でもありの製作記 第20回
ウッドデッキにフェンスを取り付ける
設計と材料
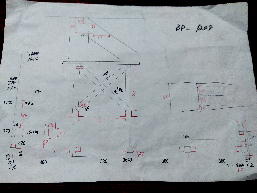

我が家のウッドデッキにはフェンスが無く、部屋が丸見えだし布団も干せない。そこで当然のようにフェンスを自作する。
まずはデザインと実測値からの図面を引く。材質はウッドデッキ用材としては一般的な、ウエスタンレッドシダーを選択。サイズは、柱材4×4 900mm 8本、横板材2×4 2100mm 3本、筋交い材2×4 1200mm 10本。グレードはプロエリート。購入先は山梨の「木工ランド」。サイズは自宅まで配達されるように、軽トラにも積めるようなサイズにしたが、結局名鉄運輸の営業所止めにせざるを得なかった。木工ランドの対応は素早く、とても良心的だった。✰✰✰✰。
柱を作る



左、柱材として購入した900mmの4×4材だが、実長は非常にまちまち。それでも全て 900mm以上はあるので、正確なサイズに全て調整し直す。
中右、長さが決まれば、金具に取り付けられる部分を塗装しておく。取り付けてからでは塗れないので。塗料はナフタデコール チェスナット(キシラデコールよりも圧倒的に安い)。キシラデコール カスタニと同系色のはずだが、大分黒っぽい。チーク色の方が良いような気がする。
柱を取り付ける



左、フェンスは後付けなので、柱を立てるステーが必要。これは幅80×縦85×85のL型金具。ホームセンターで売っている物。全部で8本の柱を立てるので、位置を正確に割り出す。まずは片側だけ金具を取り付ける。
中、下穴を開ける。
右、コーススレッドで取り付け。続いて仮に柱を置いて、他の金具を取り付ける。コーナーは90度方向に、ぐらつきの大きいところ(1枚の床材に取り付ける部分はぐらつくので)には両側+90度側にも取り付ける。



左、同様に柱を取り付ける。
中右、柱が立ったら今のうちに塗装しておく。後からでは塗れないところが多い。
横板を取り付ける



左、横板を取り付けるため、2×4材を仮載せして実測する。床材等の捻れがあり、想像以上にずれが大きい。
中、所定の長さに、又コーナーは45度にカットし、裏側の部分を塗装しておく。
右、一部は自宅の柱と雨樋を除けるように、このような形にカット。

横板をコーススレッドで取り付けたら、後でも良いが塗装してしまった(雨に濡らしたくないので)。
筋交いを作る



ウッドデッキフェンスの一番特徴的なデザイン、バッテン型の筋交いを作る。
左、1箇所につき 2本のビスで止めるよう、印をしたところにポンチを打つ。筋交いは約45度で柱に接するので、筋交いに対しては斜めにコーススレッドをねじ込むことになる。なかなか難しい。
中、3mmのロングビットで下穴を開ける。
右、今のうちに面取りをしておこう。


左、コーススレッドの頭を埋め込むために、太めのビットで適当量を揉んでおく。座繰り量を一定にするために、ガムテープを巻いて目印にした。
右、後から塗れない部分を塗装しておく。
筋交いを取り付ける



左、一部の塗装を終えた筋交いを取り付ける。一人で取り付けようとすると、腕がもう1本必要になる。そこで考えたのがゴムバンドで筋交い木を吊って位置決めをする方法。これは素晴らしいアイディアだった(自画自賛)。
中、位置決めした筋交い木を通して、柱にロングビットで下穴を開ける。
右、すかさずコーススレッドをねじ込む。これで1本の筋交いが完成。


左、こんな感じでコーススレッドが埋め込まれている。
右、片側が固定されたら、一部塗装した部分が向き合うように同じように腕吊りをして、バッテンの対になる筋交い木を固定する。
塗装して完成



左、全ての取り付けが完了したので、ガンガン塗装する。後から塗りにくい部分は先に塗ったのだが、必要以上に広範囲に塗らない方が良い。先に塗った部分ばかりが濃くなってしまい、見た目が悪い。重ね塗りをしていけば改善するとは思うが。
中、完成。ペンキ塗り立てでテカっているが、乾けば落ち着く。さらに重ね塗りをする予定。
右、外観全景。なかなか良い感じになったでしょ。