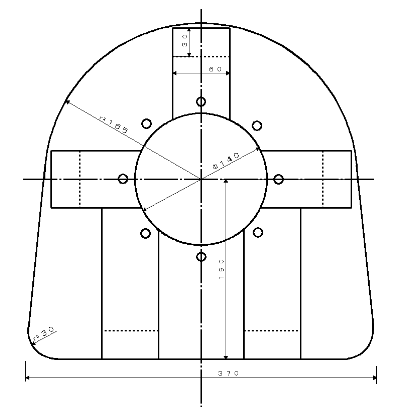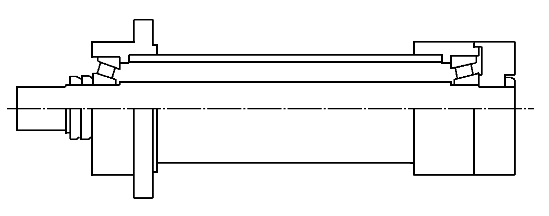 |
| 先月までで赤緯軸の説明は終了しましたので、今月はまずその組み立て図を紹介します。 図が複雑になるので、(本当は面倒なだけ?)赤経軸取り付けフランジは記載していません。 組み立て方法その他は、赤経軸の時とほとんど同じです。違う所と言えば、赤緯体は完成後も外部に露出していて、見栄えに影響するところですから、各ベアリングハウジングを溶接した後、接合部をパテで曲面を付けながら埋めました。そうした後、塗装してあります。 図の右側が望遠鏡台座取り付け部、左側がこれから説明に入ります駆動系とバランスウェイトのハウジングが取り付けられる部分です。 |