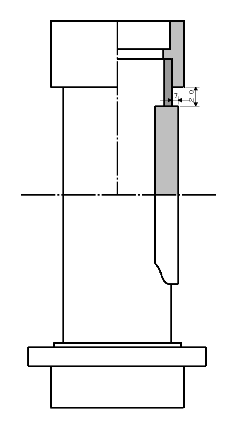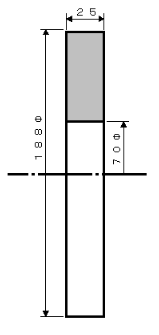 |
| 今月は赤経軸取り付けフランジについて説明します。 以前の自作赤道儀によく見られたピローブロックを使用している場合でしたら、赤緯軸を赤経軸に対して直角に設置することはさほど難しいことではありませんでしたが、この場合はパイプにフランジを固定しなくてはならないので、しばし考えさせられました。 見た目もある程度は重視したので、パイプにいきなりフランジを溶接するのではなく、埋め込むことにしました。(この方が溶接面積も広がって、強固に接続できるという利点もあります) フランジそのものは図の通り、さほど小細工はありません。材質はSSの丸棒から切り出した物を旋盤加工した物で、図にはありませんが、赤経部との接続のため、赤緯軸を避けるように6カ所のキャップスクリュー用の穴を加工してあります。 |