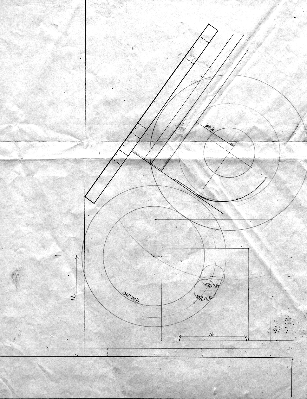|
| 今回から何回かに渡って赤経軸の駆動系について説明します。この部分は赤道儀の心臓部ですから、特に細かく説明しようと思っています。 ただ、かなり複雑なため、細かい寸法値は割愛します。(有っても無意味ですよね) 駆動系の説明は、私の設計過程に沿って説明しますが、まずは初期設計から。 上の図面は最初に取りかかった図です。左上から右下に伸びる直線が赤道儀のピラーですから、首を左に傾けて見てください。 図は、赤道儀の西側から見た物ですが、ピラーに直接取り付けてある物が先回写真で紹介したウォームギア取り付け台座です。これはピラーと同じ材料から切り出した物で、重要な事は赤経軸と直角に設置されなくてはならない事です。 ウォームギア取り付け台座に取り付けてあるのが、ウォームギアハウジングです。当初はミカゲ光器の物をそのまま使うつもりでいました。しかしこれはウォームギアがメタルタッチで支持されていて、調整が非常に難しく、下手をすると駆動系のトルクが不足する事が予想されたので、その後ピローブロックを使用した物に作り替えました。 ウォームギアハウジングの真下にあるのが、電磁クラッチです。使用した機種は三木プーリーの125-06-12A-50です。電磁クラッチは単体でも販売されていますが、そのハウジングを作る必要がありますので、ユニット化された物を探しました。ほとんどの場合、電磁ブレーキとのユニットになりますが、必要なのはクラッチなので、何社か当たってこの機種に決定しました。トルクは静摩擦トルク0.55kgfmで充分です。(他メーカーにはもっと小型の物もあります) その右上の円は、ステッピングモーターの出力ギアの位置を決定するための円です。ステッピングモーター及びその駆動装置は九州のトミタさんにお願いしました。(ST-4と組み合わせると最高です)ステッピングモーターはオリエンタルモーターのPH266と9対1ギアヘッドとの組み合わせです。 クラッチの片側にはステッピングモーターが、もう片方には、レバーシブルモーターが付きます。通常駆動時はクラッチを接続した状態で、ステッピングモーターで駆動し、高速回転の場合はクラッチを切りステッピングモーターを切り離した状態でレバーシブルモーターにより1000倍速以上を実現します。このアイディアは以前から持っていた物で、高橋さんや、昭和さんよりずっと早いと自負しています。他の機械を見ないのもこう言ったアイディアを捻り出すためで、この部分だけはこだわりたかったのです。レバーシブルモーターは日本サーボのC-21PNに可変速コントローラーのRHT8S25を組み合わせた物です。 この図は、説明したような各パーツが、それぞれ干渉しないかどうかを探るため又、各ギアの歯数を決めるために書きました。 |