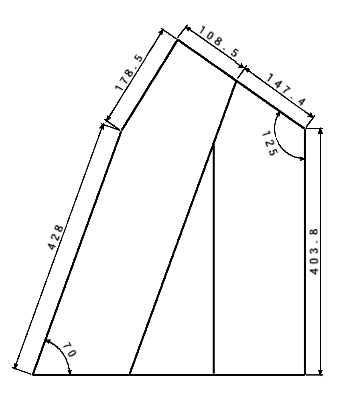 |
| 先回、台座底部の説明をしましたので、今回はその上に乗るピラーを説明します。 メーカー製でしたら台座、ピラー、(赤経軸も)等は一体型の鋳物(ダイキャスト)で作られているのでしょうが、(メーカー製を見た事がない)私にはそんな芸当はできないので、ここではH鋼で組み上げています。 使用したH鋼は、正確には、軽量H形型鋼と言い上図で見た時の幅150mm、縦193.5mmの物です。軽量型鋼にした理由は、強度的には十分ですし、H鋼の縦方向に2ヶ接続した時の(下右写真)幅が重要だったからです。 この様に、図では解りませんが、左右のH鋼は各々2ヶずつ組み合わせてあり、図の最上部に赤経ハウジングが半分沈み込む様に接続されます。最下部は先回ご紹介の台座底部に溶接されます。 |

