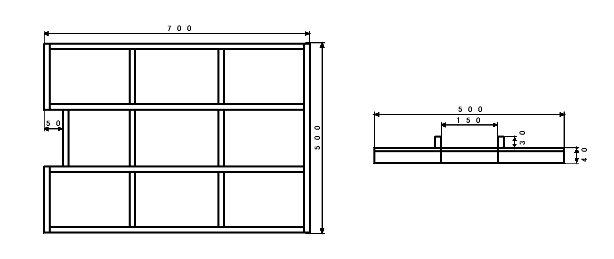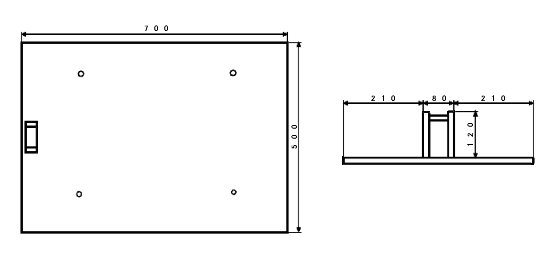 |
| 先月までに赤経軸の説明が終わりましたので、今月からはそれを取り付ける台座(ピラーも含む)の説明をします。 左図は、ドームを制作した際に立てたコンクリートピラーの最上部に、直接取り付けられる底板で、サイズはまさにピラー最上部そのものです。図中にある丸印が、ピラーに埋め込んだアンカーボルトを固定するための穴ですが、それほど正確に埋め込んでありませんので、採寸の上位置を決定します。私の場合、南北方向が約420mm、東西方向が約380mmでした(正確にはmm単位ですべて違いますが)。 右図は、極軸調整用の底板固定ベース(正確には何という名前かわかりませんが)を表しています。このベース部分が下図の切り込みの部分に挿入され、左右からボルトで押されることで、極軸の東西方向への移動を実現します。 材質は、すべてSS。底板は6mm厚の鋼板から、固定ベースは厚さ15mm、幅30mmの帯鋼から切断し溶接してあります。 |