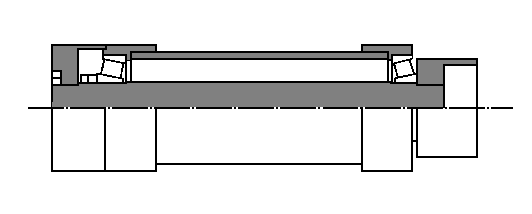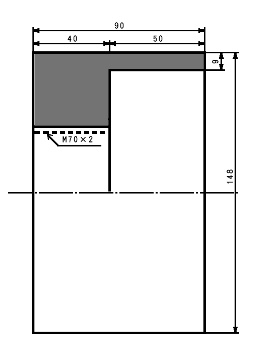 |
| 今月はまず、赤経軸のウォームホイール支持体の説明をします。 前に紹介したように、赤経軸用のウォームホイールはミカゲ光機製です。ウォームホイルのリム部は130Φですが、(図には記入してありません)精度表示で外注するのも良いのですが、私の場合は現物合わせと言うことで、加工場にウォームホイールも持ち込みました。 この部分は当初、スリ割りにしてクランプをつけるつもりでしたが、赤道儀の駆動系を2モーター方式に変更して最高1000倍速を実現したので、クランプ機構は必要なくなりました。それよりもむしろ、確実に偏芯無く固定されている事の方が重要と考えました。 実際使用してみて、30センチクラスの望遠鏡を手動で移動するのはかなり大変だと思いますし、この方が実用的です。ただ、先程の現物合わせ方式は、加工場の技術の問題が大きく効いてきますので、やはり精度指定する方が良さそうです。私の場合、わずかながらガタがあり、ピリオディックモーションを悪化させています。 この支持体は、他にも、テーパーローラーベアリングの与圧をかけるナットの役目もしています。 材質はSSで、図には記入してありませんが、ねじ部の外側に固定用ボルトのねじ加工1カ所が、ウォームホイール部には、その固定用のねじ加工が3カ所行ってあります。ともにM10のメスねじです。 |