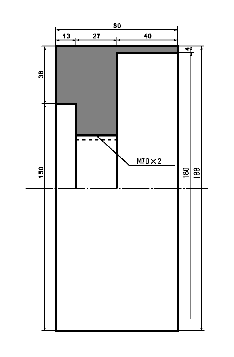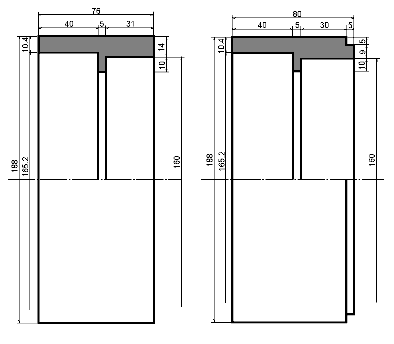 |
| 今月は、赤経軸のベアリングハウジングの説明をします。今月から、ドロー系のグラフィックソフトを使用して、図面を掲載していきます。実際に使用した図面も臨場感があって良いのですが、何しろ汚れているので、スキャンしてもまともに出てきません。この方が解りやすいと思います。ただし、製図そのものは未だに素人ですし、正面図は省略してあります。 赤経軸に使用したベアリングは、円すいころ軸受の30315Uですので、ベアリング外径が160mmです。右図が北端用、左図が南端用で、ともに図の左側(内径165.2mmの部分)が、先月の赤経軸ハウジングの部分に被さります。材質はSS。丸棒からの削り出しです。 使用したベアリングは基本定格荷重が23,300kgfありますので、乗用車くらいなら楽にもてます(他が壊れるか)。 このベアリングの固定方法は、南端は次回紹介するウォームホイール支持体ですが、北端はダブルナットによる固定です。そのため、下図の右側にそのための空間を40mm設けてあります。ナットはベアリング用のAN15です。 前後しますが、図面には精度を記入してありません。今までも、そしてこれからも精度はh7もしくは、H7(要するにベアリングの公差)にしてあります。 苦労話を一つ。 このような形状の部品はこれからもいくつかありますが、少しでも自分で手を下そうと思い、当初は自分で旋盤加工するつもりでした。そこで、先に大きく中身をくりぬこうと思い、200mmのSS丸棒から切り出したブランクのくりぬく部分にドリルで穴を連続してあけ、たたき抜くことを試みました。2つほど実際にやってみましたが、人間のやることではないと観念し、旋盤加工もあきらめ、加工所に持ち込んだところ、「チップの刃が飛んでしまい難儀した」とのこと。SSなら、無垢材から削りだした方が簡単だそうです。 素人考えは、思い違いの方が多いものです。 |