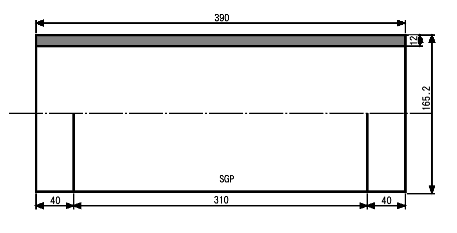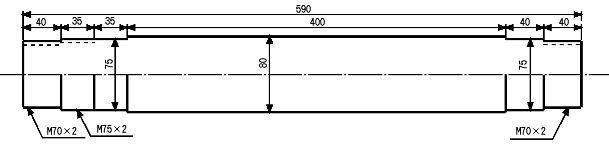
先回の図面を見ていただくと解ると思いますが、形状が少し違います。実はこれは2代目なのです。
初代赤経軸の図面を引いて、実際に外注したのが1997年だったと思います。この頃は、外注先1つとっても、何も知識もなく、知り合いを訪ね歩いたあげく、ある加工場を紹介していただきました。
結局、他に当てもなかったので、そこで作っていただいたのですが、なんと加工料が7万円もしたあげく、一部寸法違いをしていました。これが、先回の図面、初代赤経軸です。
ちょうどこの頃、私の長男が生まれ、何をするわけではないのですが、はらはらどきどきの毎日で、望遠鏡どころではなくなってしまいました。それでこの赤経軸は4年近くも、ほったらかしの運命を辿ることになりました。
結局、7万円の高価な赤錆の棒が出来上がり、赤緯軸などと共に作り替えることとなりました。
初代からの変更点は、ウォームホイールのクランプ固定をやめ、フランジに直接固定として、ウォームホイールの貫通部分を省略した点です。
画面では解りにくいと思いますので、言葉で説明しますと(今後もそうします)全長590mm、最大径80mm、ベアリング部径75mm、ベアリング間隔400mm、図面右側のウォームホイール固定ハウジング取り付け部が、M70 P2の雄ねじ、図面左側のベアリング予圧部がM75 P2の雄ねじ、望遠鏡取り付け座固定部がM70 P2の雄ねじ。材質S45C、加工費何と、8000円でした。株式会社 マルニシ 機工部の皆さん、大変お世話になっています。この場を借りてお礼申し上げます。