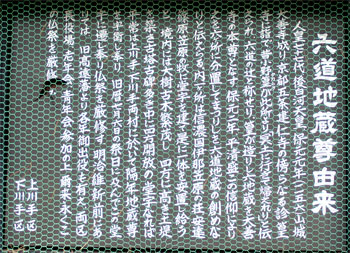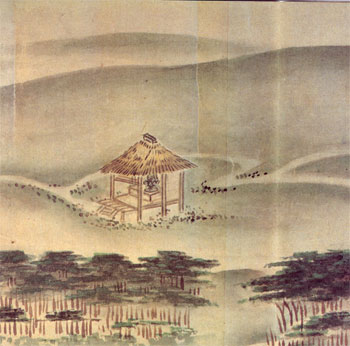|
六道とは |
||
由来書きの看板です。ただ、文中「診皇寺」とあるのは、小野篁の説話が取られていることから、京都六道の「珍皇寺」のことではないかと思います。 |
『高藩探勝』より「六道野経」 |
||
|
祭礼
お祭りは、今は8月6日に、上川手・下川手の老人会の人たちが中心になって行われています。特に、この年新盆を迎える家では、「霊迎え」といって、必ず参拝することが慣わしとなっています。 |
||
|
|