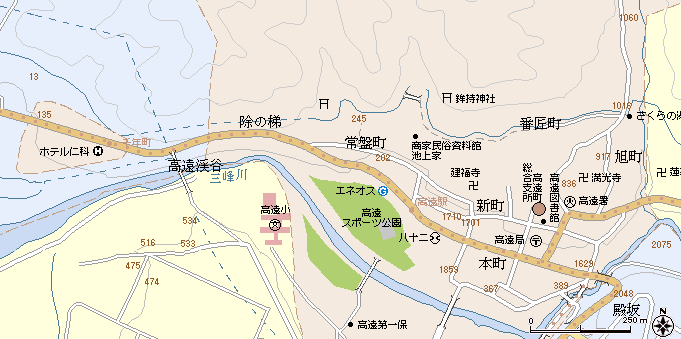鉾持神社
延喜式外にして、伊那郡の大社なり。(中略)鉾持社旧記曰、安和2年己巳年4月、信濃守源重之卿、伊豆箱榎、三島の三社を、伊那郡笠原ノ荘に勧請と、社伝に見へたり。治承4年、板町30町の地頭石田刑部、鎌倉勢と戦て敗軍、鎌倉勢三社を軍榊と崇め利あり、故に勝軍の地北村に祭之。養和元年辛丑、鎌倉郡代として、日野喜太夫宗滋、30町の地を賜り、板町に住む。元暦元年甲辰正月に至り、三社を北村より同村島崎へ奉遷。歳旦の遷宮に依て、若宮社と奉称。文治元乙巳年日野喜太夫嫡男、目野源吾宗忠、若宮三社を安和勧請之旧地に奉遷の時地形を平均せしに、一つの鉾を得、因之神名を鉾持社と奉崇。(『上伊那町村誌』より)
大意は、「平安時代、信濃の国主であった源重之が伊那郡笠原に社殿を建てたのが始まりで、変遷の後、現在地に社殿を建てようとしたところ、地中より「鉾」が出たので、鉾持社と名付けた、」とあります。
毎年2月11日の「だるま市」には、だるまを求める人で賑わいます。
また、境内には源重之の歌碑があります。
源重之
平安時代中期の歌人。清和源氏。生没年未詳(60歳余か?)。三十六歌仙の一人。陸奥守藤原實方にしたがって陸奥の国に下向し、彼地で没したとも。
家集に「重之集」があり「拾遺和歌集」以下の勅撰和歌集に採られる。
碑の歌
しなのなる伊那にはあらじかいがねの
つもれる雪の解けんほどまで |